現在の雇用の49%がロボット・AIに奪われる。「日本3.0」時代の企業に求められる7つの主要機能とは?
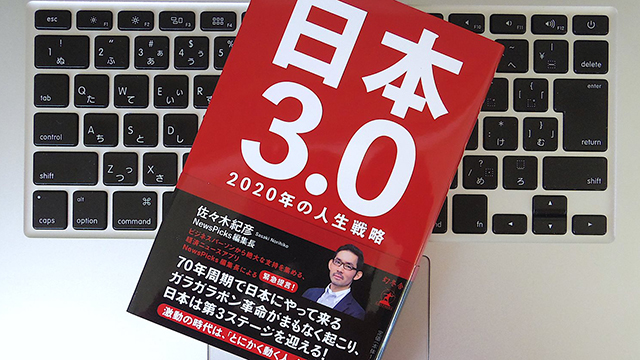
『日本3.0 2020年の人生戦略』(佐々木紀彦著、幻冬舎)の著者は、経済ニュース共有サービス「NewsPicks」編集長としての立場から、日本の未来を危惧しています。経済の低迷が続いているとはいえ、世界のなかで日本はまだ相対的に豊か。しかし、そんな平和な時代も終わりを告げようとしているというのです。
安寧の日々が続くのもせいぜい2020年まで、それに前後して日本には、ほぼ確実に修羅場が訪れる。しかもそれは、100年に1度といってもいいくらいインパクトのあるものとなるのだといいます。
日本の近代は、1868年の明治改元から始まり、その第1ステージは、1945年の敗戦によって幕を閉じました。その後、敗戦から立ち直った日本は、奇跡の経済成長を遂げ、輝かしい「近代の第2ステージ」をつくりあげました。しかし、その時代にも終わりが近づいています。戦後モデルのガラガラポンがあらゆる領域に迫っているのです。
2020年前後から始まる「日本近代の第3ステージ」、通称「日本3.0」は、これまでとはまったく異なる思想、システム、人を必要としています。
(「はじめに」より)
つまり日本は、明治改元から敗戦に至るまでの日本近代「第1のサイクル」である「日本1.0」、敗戦から2020年までの「第2のサイクル」である「日本2.0」を経て、3段階目にあたる「日本3.0」に入ろうとしているということ。
そして、そのヒントとなるのが、社会学者で京都大学名誉教授の竹内洋氏が提唱したという「ガラガラポン革命」だそうです。「ガラガラポン」の語源は、くじの入った箱を振ったり回したりして、くじを振り出すときの音。そこから転じて、社会のシステムを根底からガラッと変えたり、組織の人員配置をすっかり入れ替えたりすることなどの意味で使われるようになったというのです。
そこで本書では、第3のガラガラポン革命である「日本3.0」に、どのようなことが起こるのかを克明に解説しているわけです。しかし、だとすれば気になるのは「将来の仕事」ではないでしょうか? そこで第4章「日本3.0と仕事」から、いくつかのポイントを引き出してみることにしましょう。
日本の雇用の49%がAIに奪われる?
ご存知の方も多いと思いますが、2013年9月、オックスフォード大学でAIを研究するマイケル・オズボーン准教授が「AIやロボットによって、米国の雇用の47%が消える可能性がある」という予測を発表。以来、世界中に「AI・ロボット脅威論」があふれています。
また、米国を対象にしたその論文だけではなく、のちに日本に関しても野村総合研究所と組んで601の分析を行なっているのだそうです。その結果として出たのは、日本の雇用のうち49%がAI・ロボットに代替される可能性が高いとの結果。この数字は、米国の47%、英国の35%をも上回る比率。つまり、日本の半分の仕事が失われるかもしれないということになります。
ちなみに「消滅リスクの低い仕事」は、医者、先生、編集者、アートディレクター、コンサルタント、バーテンダー、保育士など、人とのコミュニケーションが必要で、経験やアイディア、機転が求められるもの。一方、「消滅リスクの高い仕事」としてわかりやすいのは、受付係、タクシー運転手、レジ係、データ入力係、自動車組立工といった仕事。これらの定型化しやすい仕事は、駅の切符切りの人たちが自動改札になってお役御免となったように、徐々に減っていくというのです。
とはいえ日本はすでに人口減少に突入しており、特に地方では人出不足が深刻。だから、これらの仕事がAI・ロボットに置き換えられていくことが、雇用問題になるリスクはあまり大きくないそうです。むしろ、ロボットやAIは労働力不足を補うものとして歓迎される可能性すらあるのだともいいます。
しかも、たとえばコンビニで自動レジが導入され、レジ係のニーズが減ったとしても、棚の商品の入れ替え、レジでのお弁当の温め、店の掃除などの仕事は人間がやる必要があります。減る仕事がある一方には、増える仕事もあるわけです。そのため、一気に仕事が減るとは思えないというのです。つまり、AI・ロボットで仕事が激減するといったシナリオは誇張されすぎているということ。(226ページより)
会社に残れるのは7つのプロだけ
究極的に、今後の企業はどんどん人数が少なくなり、主要機能は次の7つに絞られていくだろうと著者は推測しています。そして、なにをやっているのかよくわからない、”中途半端なホワイトカラー”はどんどん居場所を失っていくそうです。さて、7つの主要機能とは、どのようなものでしょうか?
(1)少人数のトップマネジメント
社長と取締役など経営メンバーであり、仕事内容は「決めること」と「ビジョンを出すこと」「リーダーを発掘・育成すること」、そして「結果を出すこと」。これまでのような、過去の実績に対する名誉ポストとしてのポジションはなくなっていくといいます。
(2)スリム化されたバックオフィス
筋肉質なサポート集団。バックオフィスの事務処理はAIによって効率化され、最低限の人数で行なう体制になるそうです。メンバーは、資金調達などのファイナンス、人間的要素が強い広報・IR、人材採用、リーダー教育といった戦略業務が中心。
(3)チームづくりに長けた中間管理職
組織やチームをうまくつくるうえで、今後も中間管理職は不可欠。ただし、組織はよりフラット化し、レイヤーは1、2層にとどまるといいます。主たる仕事は、多様な人材を束ね、モチベーションとポテンシャルを引き出して「結果を出す」こと。
(4)人間味あふれる営業
もっとも人間くさい領域である「営業」は、AIによって代替されにくい仕事のひとつ。そして、今後いっそう大切になるのは、対面とデジタルのコミュニケーションを組み合わせて信頼関係を築く能力、うまく製品・サービスの魅力をプレゼンする能力。
(5)ストーリーを創れるマーケティング・ブランディング
商品・サービスのコモディティ化が進むなかにおいて、競争力のカギを握るのはマーケティング。直感とデータによって時代のトレンドを読み、「モノ」と「コト」をうまく組み合わせてストーリーを創り、優れたブランドイメージを生み出せるかが問われるわけです。
(6)センスと粘りのある商品・サービス開発(+製造)
いわば、創るプロ。いくら営業力、マーケティング力があっても、肝心の製品・サービスの力が乏しければ成功は望めないもの。斬新な製品やサービスを生み出していくとともに、日々、製品やサービスを改善していくPDCAの能力が求められるといいます。
(7)成長を生む「海外事業」「M&A」「新規事業」のプロ
もはや、ひとつの会社内で生み出すイノベーションには限界が。そんななか新たな主役になるのは、海外市場を開拓しローカル人材をマネジメントするプロや、いい企業を見つけて買収し、成長させるプロだという考え方。
端的にいえば、「決めるプロ」と「サポートのプロ」と「チームづくりのプロ」と「売るプロ」と「伝えるプロ」と「創るプロ」と「買うプロ」。この7つのプロが会社の主役となり、企業をリードしていくというのです。よって、この7つの領域のリーダーの力と、その戦略を実現する「現場の力」が、企業の競争力を決定づけることになるということ。
かつての日本企業では皆が出世を目指し、皆が一定年齢までは平等に出世するシステムが主流でした。しかし今後の日本企業では、(分野や企業の質にもよるとはいえ)リーダーを担ったり、目指したりする層は社員全体の1割以下になるはずだと著者は断言しています。
そのほかの社員は、各領域のリーダーのフォロワーとして働くかたち。そのなかには、若手の修行中の社員もいれば、自分の専門分野で職人のように働く社員もいれば、出世は目指さずワークライフバランス重視で働く社員もいるというかたち。”キャリア横並びの時代”は、完全に終わるということです。(232ページより)
新しい時代に求められるのは、失敗しても這い上がり、しつこく挑戦する人間だと著者は記しています。それは、常識を疑い、ゼロからイチを生み出せる人間。日本にとどまることなく、世界に飛び出す人間。なんにでも好奇心を持ち、貪欲に知を求める人間。自己愛を超えたプリンシプル、思想を持った人間。
いずれにせよ大切なのは、はじめの一歩を踏み出すこと。そうすれば、いまとは違う世界が広がるというのです。そのとき、目の前に広がる光景をしっかりと視野に収めるために、本書をぜひ読んでおくべきだと感じます。
(印南敦史)
元記事を読む
関連記事
| ご質問は人工知能が承ります |
| 2016リオでは人工知能が活躍 |
| 【世界初!ロボット弁護士現る】イギリスでは人工知能が異議申し立てをするらしい |
- ブーストマガジンをフォローする
- ブーストマガジンをフォローするFollow @_BoostMagazine_











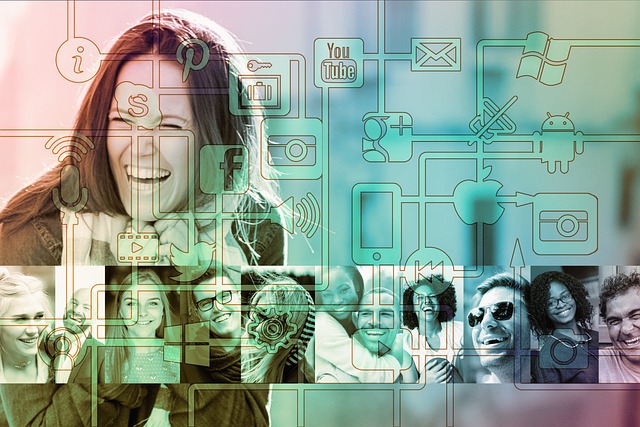
 【PR】PostPetの「モモちゃん」に会える!桜の季節の中目黒で笑顔になれるひ
【PR】PostPetの「モモちゃん」に会える!桜の季節の中目黒で笑顔になれるひ 「24時間可愛いなんて無理」本音から知る女性社員への接し方とは?
「24時間可愛いなんて無理」本音から知る女性社員への接し方とは? 我が子の姿を美しく残す!子供の撮影テクをプロに聞いてきた!
我が子の姿を美しく残す!子供の撮影テクをプロに聞いてきた! 雨・雪の日の愛犬との散歩も楽しいね
雨・雪の日の愛犬との散歩も楽しいね 赤い悪魔を追い詰めた西野JAPAN、足りないものとは
赤い悪魔を追い詰めた西野JAPAN、足りないものとは








 Faceboook
Faceboook Twitter
Twitter